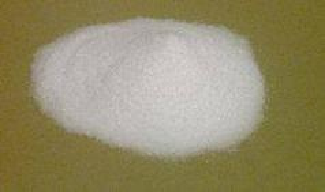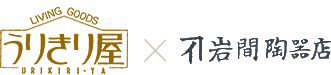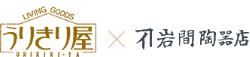こだわり
私達日本人はいつの頃からか、器と料理に季節を感じ生活を楽しんできました。
季節に合わせ、素材に合わせ、おもてなしの目的に合わせ、
そのときどきに形や色彩に変化を持たせた器を選び、粋な盛り付けをし、食文化や食卓を彩ってきました。
四季に合わせ衣替えをするように、器も替える…
春夏秋冬のある日本に生まれたからこそ、日本人らしい器の味わい方をしてはいかがでしょうか。
良い器を長く大切に使っていくことはもちろんですが、器にもやはり流行があります。
うりきり屋ではただ安いだけでなく、今の生活に合うようなしゃれたデザインでしっかりしたものを揃えております。
心を豊かにしてくれる――
そんなお気に入りの器の数々をお客様にお届けしていきたいと思います。
陶器のイロハ
毎日、何気なく食卓に並んでいる器
手にとったことがないという人はほとんどいないでしょう…。
「器」と一口に言っても、地域によって素材や形はさまざまです。
ここでは、器の種類や違い、扱い方についてご紹介していきます。
また、お客様よりいただいた器に関するご質問についても、この場でお答えしていきたいと思います。
【陶器と磁器の違い(特徴)】
器(焼き物)には大きく分けて、陶器と磁器の2つがあります。
この2つの根本的な違いは原料です。陶器の場合は粘土、磁器は陶石と呼ばれる石の粉(石英・長石など)と粘土物質を原料としています。
右の表にも書いてある通り、陶器には吸水性があります。
吸水性のある器は電子レンジには不向きですので、ご使用にならないようご注意ください。
また磁器のものでも、金や銀が絵付けで使われているものは、電子レンジではご使用いただけません。
| 陶器 | 磁器 |
| 吸水性があり 透光性がない |
半透光性で 吸水性がない |
| 焼成温度 900~1200℃前後 |
焼成温度 1200~1400℃前後 |
| 熱の伝わりが遅い | 熱の伝わりが早い |
| はじいた時の音が 濁音(鈍い音) |
はじいた時の音が 金属音に近い(澄んだ音) |
【使い始めのウラ技】
【陶器(土もの)】
土ものの器は使用前に煮沸していただくと良いでしょう。
そうすることで、器を焼き締めるので丈夫になります。
器がかぶる程度の水で約30分ほど煮沸し、自然に冷めるまで待ちます。その際にお米のとぎ汁を使うと、土肌の目を埋めるので、汚れが染み込みにくくなります。
また、料理を盛り付ける前には器を充分水につけ、水分を含ませましょう。
料理の匂いや汁気、油などが染みにくくなります。
【土鍋】
土鍋の手入れはお店でもご質問が多いので、土ものとは分けてご説明します。
使い始める前にまずお粥を炊き込んでください。
(1)鍋の裏底に水気がないことを確認してください。
(2)土鍋8分目まで水を入れ、水量の1/5以上のご飯を入れ必ず弱火にします。
(3)吹きこぼれないよう、また底に焦げ付きができないように十分注意しながら、のり状になるまで、最低でも10分以上炊き込みます。
(4)火を止め、土鍋が十分に冷めてから、お粥を取り除き水洗いします。
(5)よく乾燥させてからお料理にご使用ください。
お粥が難しい場合は、土鍋8分目程度の水に大さじ1杯~2杯の小麦粉をよく溶いて10分以上煮立てていただいても効果があります。
水やとぎ汁よりも、土のアクが抜け吸水性を防ぐので、土鍋や目の粗い陶器(土もの)は、こちらの方法が良いと思います。

【陶器(土もの)の特徴】
【斑紋】
陶器(土もの)には吸水性があり、水につけると“斑紋(はんもん)”が浮かび上がりますが、ご使用には差し支えありません。
【貫入】
器の釉薬をかける前の生地部分と釉薬部分では、窯に入れて焼くときの縮み具合(収縮率)に差があります。そのときに釉薬面にできるヒビのことを“貫入(かんにゅう)”と言います。こちらは土もののデザイン(加飾)技法のひとつで、商品不良ではありません。
貫入の入りを楽しみながら、長くご愛用いただければと思いますが、なるべく貫入を目立たせないように愛用するには、ご使用前に水またはお湯に器をつけたり、ご使用後はなるべく早く洗ってよく乾燥させるのを心がけると効果的です。
【使い終わったら・・】
【陶器(土もの)と土鍋】
使い始めでもご説明しましたが、陶器(土もの)と土鍋には吸水性があります。
ご使用後はなるべく早く洗いましょう。
中性洗剤で汚れを落とし、よくすすいでください。
洗った後は、よく乾燥させます。土鍋の場合は、底面を上にしてしっかりと乾燥させてください。
■土臭さや料理の匂いがついてしまった場合は‥
土鍋に8分目まで水を入れ、茶殻(緑茶やほうじ茶)をひとつかみ入れて10分程煮立てます。
かび臭さには‥
土鍋に8分目まで水を入れ、お酢大さじ2~3杯を加え、10分程煮立てます。
こちらの方法をお試しください。
■焦げ付いてしまった場合は‥
土鍋に水を入れ、重曹を小さじ1杯くらい入れて沸騰させ、ぐつぐつ煮立てた後、木べらでこそげ落としてください。完全に落とすことはできませんが、多少効果があります。

【電子レンジに使用できる金絵付け】
金・銀絵付け食器は、電子レンジやオーブンで使用すると、パチパチと音を立ててスパークを起こし、金・銀の絵付けが剥がれてしまいます。
しかし、電子レンジなどでも使える金絵付けのものもあります。
「電子レンジ金」と言われるものと「金雲母」を使用している絵付けです。
通常の金・銀絵付けは、純金に近く導電性が高いために、スパークしてしまうのですが、「電子レンジ金」は金に特殊な加工が施されていたり、プラチナなど金以外の原料が使用されていたりすることから、導電性がなく電子レンジに入れてもスパークしません。
「金雲母」も同じく金ではなく雲母という原料を使用しているためにスパークしません。見た目がザラザラしていて、マットなものが多く、柔らかな金色といった雰囲気で人気があります。
写真は金雲母の商品です。うりきり屋では華やかさと上品さがある金雲母の商品を多数ご紹介しています。
金の部分を触ってみてザラっとしている商品は金雲母の可能性がありますので、ぜひ店頭でご質問ください。また見分けが難しいものもありますので、購入時に販売元のお店で確認されると確実だと思います。

【急須の茶渋の取り方】
急須の中に重曹と水またはお湯を入れ、5時間くらい置きます。
重曹の代わりにポット用の洗浄剤を使ってもいいようです。(量は加減してください)
漂白剤は匂いが移ってしまう可能性があるので避けてください。